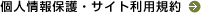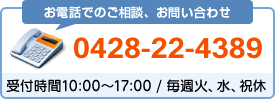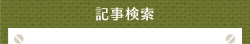スギ花粉

スギ花粉の飛散がはじまり、花粉症の季節になりましたね。
私自身は、花粉症ではないので大丈夫なのですが、周りの人たちは、常にマスクをして、目が赤かったりして、大変そうです。
スギは、一昔前に山々に植林していた木。
以前にはスギを育てて適宜伐採し、建築資材として使われていましたが、今では主流が輸入材となって、林業も盛んでなくなり、放置されたスギの木が増えました。
そうして、スギの花粉も増えるとともに、花粉症の人も増えたといわれています。スギの花粉症はいわば、現代病ともいえますね。
完治するというわけではないですが、薬ではなく日頃の食べ物も花粉症対策として、おすすめのものがあります。今、体をあたためるということで注目されているショウガは、花粉症にも有効の食べ物です。
ショウガのなかに含まれているショウガオールという成分がくしゃみや鼻水に効果があるのだそうです。
ジンジャーティを飲んで、体をあたためて、つらい花粉症が和らぐといいですね。
ふきのとう

ウグイスが鳴いたら春だなとか、梅の花が咲いたら春だなとか、春を感じる知らせは、花が咲いたり、冬の間みられなかった生きものの姿を感じたりだったりします。
我が家の前にも、春の訪れを感じさせてくれるものがあります。蕗の薹(ふきのとう)です。2月もおわり頃になると出てくるのです。
我が家は少しじめっとしているので、蕗の薹にとってはちょうどいいみたいです。
蕗の葉っぱは多くみるのですが、蕗の薹は少ないで、みとれているうちに食べ頃を逃してしまう年もあります。
たくさんあるところから、少し採って、「ふき味噌」を作ります。
蕗の苦みがおいしいご飯のお供です。春の味はほろ苦くて、パワーを感じます。
今年はどのくらい、蕗の薹が出てくるのか楽しみです。
芽かぶサラダ

3月は天然わかめの解禁とのことで、美味しいワカメが手に入ります。
冬に天日干しされた乾燥わかめも美味しいですが、やはり生ワカメは格別です。
3月の海に行くと、打ち上げられたワカメを拾うことがあります。
上の方の柔らかい部分はいつものワカメ。お味噌汁に入れて食べたりしますが、根元の部分のひだの部分、肉厚の「芽かぶ」がとても美味しいのです。
よく洗って砂をとり除き、ゆでると、さあっと色がきれいな緑に変わるのも、思わずみとれてしまいます。
刻んで、豆腐と一緒に青じそドレッシングをかけて食べるのがお気に入りの食べ方です。
芽かぶには、通常食べる部分よりも、ミネラルがたっぷり。
なかでも、フコダインというねばり成分は、美容でも注目されている血液をサラサラにしてくれます。
日々の健康は食べ物から。美味しくいただきましょう。
オオイヌノフグリ

まだまだ寒い日が続きますが、暦のうえでは、もう春。二十四節気の「雨水」が過ぎて、雪から雨に変わる頃、雨水がゆるみ、草木が芽吹き始める頃です。
足下の春の野の草たちは、小さな葉をバラのように放射状に地面に広げて、寒さに耐えています。
まだ時折、寒さが厳しい日もありますが、春はそこまで来ています。
小さな青い花を咲かせるオオイヌノフグリ。オオイヌノフグリは、春一番に花を咲かせる野の花です。
別名を、「星の瞳」といい、その名前のように青くかわいらしいお花です。
お日様がよく当たるときに花が咲きます。曇りの時には花を閉じています。
オオイヌノフグリの花は、小さな花を咲かせて、虫が花粉を運んでくれるのを待っています。
焼きみかん

「こたつでみかん」は、日本の冬の代名詞。
今年は、地元のおじいたちに、みかんのあたらしい食べ方を教えてもらいました。
それは、「焼きみかん」。
作り方といっても、何するわけではないのですが、焚き火のなかにみかんを入れるだけ。
みかんの皮が焼けて、少し黒くなったくらいで、火から出します。
やけどしないように気をつけて。
皮をむいて、ふだんのようにみかんを食べるのですが、実が濃いオレンジ色になったような気がします。そして不思議なのですが、甘いのです。
焼くと甘さが増すみたいです。
あったかいみかんなんて、とも思っていましたが、甘くて美味しくてびっくりです。
寒い冬に、アツアツのみかん。
発見の味でした。
春の雪

うるう年の2月さいごの日。
暦の上では春。首都圏では、大雪になりました。
大雪といっても積雪数㎝。東北の雪のレベルでは到底ありませんが…
かと思えば、沖縄では寒緋桜が咲いている頃でしょう。
東西に伸びる日本列島を感じますね。
首都圏では、積もるような雪は今年二度目ですね。
今年は、寒い冬だったように思います。
水分の多い雪でした。
都心の雪ですね。以前蔵王にスキーに行った時、スキーウェアに降った雪は結晶がしっかりみえて、とても綺麗だったのを思い出しました。
家の前を、次の日の朝に雪が凍って滑らないように、雪かきしました。汗かきました。
もう3月。3月の雪だるま。
春なんだか、冬なんだか。この雪が止んだら春、でしょうか。
雪かき

実家に帰省していた二日目の朝。
窓から外を見ると、昨日にも増して雪が積もっていました。
子どもの頃は見慣れていた風景ですが、大人になって別の地域で暮らすようになると、雪国の大変さが分かりますね
暖房からなかなか離れられない私とは対照的に、子供たちは「ゆきだるま作ってくる!」と朝から元気いっぱいで庭へ遊びに行きました。
そのうち母に「あんたもゴロゴロしてないで玄関の雪かきでもしてきなさいよ」と言われてしまったので、手袋・長靴・コートを羽織って私も外に出ました。
最初は寒かったけど、雪かきしているうちに段々と身体が暖まってきたようです。
もしかしてこれはダイエットにもちょうど良いかも…。
なんて思いました。
雪かきが終わり、子供たちと家に戻ると母がお餅を用意してくれていました。
美味しいけど、雪かきで消費したカロリー以上に食べてしまったので、雪かきはダイエットには向いていません!
ふゆめがっしょうだん(絵本)
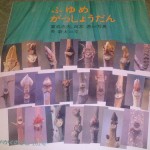
「ふゆめがっしょうだん」は、子どもの本の月刊誌、福音館の「かがくのとも」の202号(1986年1月号)の本です。「かがくのとも」はどれもおすすめなのですが、この本は、とくにお気に入りの一冊です。
この「ふゆめがっしょうだん」は、ハードカバーでも出版されています。
たくさんの木々の冬芽が出てきて、たくさんの冬芽の表情をみせてくれます。
ミミズクのような顔、ウマのような顔、いろいろにみえる冬芽の表情。
ページをめくるたびに、かわいい冬芽たちに会えて、たのしい気分になります。
この本をみたら、冬の木々がちがってみえてくるのではないでしょうか。
長新太さんが添える文も、とてもたのしい気分にさせてくれる文で、小さな子どもから大人まで楽しめる絵本です。
我が家の人気フルーツ

果物って美味しいですよね!
私をはじめ、我が家はみんな果物が大好きです。
特にその時期の旬の果物となると、どれだけ買ってもアッという間になくなってしまいます。
今日も子供たちを連れて買い物に行くと、「お母さん、いちごがあったよ!」と大はしゃぎの子供たち。
いつもは「オヤツが欲しい」とねだる子供たちですが、こうなるともういちご以外は目に入らないようです。
最近の厳冬で、野菜も果物も高いんです・・・
だけど、今の時期のいちごって本当に美味しいですよね。
ただ甘いだけじゃなく、酸味とのバランスがちょうど良くて、子ども達だけで一パックくらいは簡単に食べてしまいます。
でも食べるたびに一人一パックは流石に買えないので、今日は夕食後のデザートと言うことで一パックだけセール品を購入しました。
好きなデザートがある時の子供たちは、ご飯を食べ終わるのが本当に早くてびっくりです。
2/19 青梅マラソン
こんにちは! 河辺駅北口店です。
明日は青梅マラソンのため、河辺駅南口周辺、奥多摩街道ならびに青梅街道の一部が車両通行止めとなります。
通行止めの時間帯は現地でのご案内については、徒歩等になりますので、予めご了承いただきますようお願いいたします。
なお、河辺駅北口店の周辺(河辺駅北口~新青梅街道)は、通常の通り通行可能です。
お気軽にご来店ください。
よろしくお願いします。
青梅マラソン公式ホームページ