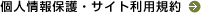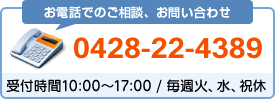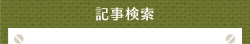節分
かきぞめ
冬のハイキング
冬は寒いから、外に出かけるのは億劫になりがちですが、冬は近場の山歩きにも行けるシーズンです。
夏のヘビやハチを心配することもなく、山のなかを歩くことができます。
寒さも歩いていれば、時に汗をかくほどで、歩いている最中はさほど寒さも感じることもなく快適です。
年末の大晦日に日頃歩いている永山ハイキングコースを歩きました。
小鳥たちの声をききながら、見晴らしの良い景色をみたり、この一年を締めくくる良き日となりました。
のんびりと冬の陽射しを浴びながら、休憩時のあたたかいお茶も、疲れを癒すひとときです。
この寒さのなかでも、冬芽はふくらんでいたり、春の息吹も感じられ、木々も寒さに耐え生きているんだなあと心が温かくなる思いがしました。
どんど焼き
年末に飾ったお正月飾りや書き初めを燃やす、どんど焼き。
(さいと焼き、左義長ともいわれます)
お正月に招き入れた、年神様やご先祖をお送りする送り火です。
丸餅を焼いて食べました。
このお餅を食べると、この一年病気にならないといわれています。
じっくり火であぶったお餅は、とても美味しかったです。
焼やした灰も、なにかいわれがあるのではないかと調べてみました。
灰を畑や田んぼにその年の作柄が良くなるようにとまいたり、家の周りにまいて魔除けにしたり、家内安全、無病息災を祈るのだそうです。
燃やして残る灰までも、ちゃんとご利益があり、意味があるのですね。
今年はまいてみようかな・・・なんて思っています。
霜柱

寒さがますます厳しくなったこの頃ですが、今週は更に冷え込んできました。
霜が降りた朝がずっと続き、いよいよ氷と霜柱の冬。
水たまりには氷が張って、地面には霜柱が立っていました。
街の地面はほぼ舗装されていて、一日の暮らしのなかのすべてで、歩く地面は土の地面ではない、という人も多くいるかと思います。
霜柱をみると、子どもの頃、うれしくて踏みしめたこと、シャクシャクという音を思い出します。
地面が氷点下になってできる霜柱。
地中の水分が毛細管現象によって地表に吸い上げられた際に凍り作られてゆくのだそうです。
自然の造形美を感じます。
冬には冬の美しさ。
朝日が当たる前のおたのしみです。
七草がゆ 〜五節句〜

1月7日は、一年の豊作と、無病息災を願って七草がゆを食べるということは広く知られているところですが、よく調べてみました。
旧暦で、「人日(じんじつ)」といって五節句の一番目の節句にあたり、立春の春の到来を祝う料理の名残として、七草粥があるのだそうです。
五節句は、上巳(じょうし)の節句(桃の節句)、端午の節句(こどもの日)、七夕の節句、重陽の節句(9月9日)と続きます。
まだ、野の草としての七草は、芽生え始めたばかりのものが多いですが、旧暦でいえば、ほぼ一ヶ月後に行われる行事なので、立春をむかえ、七草ももう少し成長していると思います。
今年は、旧暦の人日で、七草粥をしたいと思っています。
旧暦
新年を迎えましたが、今年は年初めから、旧暦(太陰暦)をより意識して過ごしてみたいなと思っています。
日頃、二十四節気を意識する事は多いですが、花の開花や生き物を見るにつれ、暦は適切に四季をあらわしているなあと思います。
太陽暦と旧暦はほぼ一ヶ月ずれていたり、閏月があったりしますが、二十四節気は、ほぼ例年同じ頃にやってきます。
その巧みな暦の由来に関心するばかりです。学ぶべきことが多そうです。
今日頃使っている太陽暦は、日本では明治に使用されるようになりました。
日本において、より長い歴史を持っている旧暦。
月の暦を意識してみたいと思います。
まずは、旧暦のお正月。
旧正月は、1月31日です。
お餅
謹賀新年 2014年
あけましておめでとうございます。
新年の門出に当たり謹んでご挨拶を申し上げます。
河辺駅北口店では、平成26年1月5日(日)より、新年の営業を開始いたしました。
この「部屋ぴた!賃貸」は、昨年、ご要望をいただきました機能追加を行い、ご評価と多くのお問い合わせを頂き、誠にありがとうございました。
さて、昨年を振り返りますと、世界経済の不確実性をはらみながらも、安倍内閣における金融緩和、財務政策をはじめ、堅調な株価、緩やかな景気回復と、多摩地域における不動産取引は目を見張るものまでには至りませんでしたが、弊社でもその一端を感じ取ることが出来ました。
オリンピックの東京開催決定といった希望のあるニュースも重なり、より一層の景気回復の期待は増し、その期待を実現へと変化させるべく、弊社もより前進すべき1年にしたいと考えております。
栄和不動産は、環境の変化に対する緊張感、ならびに集団的規律を保ち、前向きに、そして絶え間なく地域経済の活性化と「より良い住まい」の環境実現に向け、変わらず挑戦を続けていきたいと思っています。
本年も皆さんとご家族が希望に満ちた一年を送ることができますよう祈念して、今後とも更なるご支援、ご愛顧のほど引き続きよろしくお願いいたします。
かぼちゃの種

かぼちゃの旬は、夏から秋にかけてです。
もうそろそろ、おわりの季節になりますが、かぼちゃの種はいつも取り除いて食べることが多いと思いますが、たくさんでてきますよね。
お菓子の材料でよく売られている、パンプキンシードは白い殻のなかにある緑の種です。
種もおいしくいただける、ということですね。
某有名クッキングサイトでも、かぼちゃの種で検索するといろいろ出てきます。
かぼちゃの種をオリーブオイルをひいたフライパンで炒って、塩をふり食べてみました。
ぱちぱちと音がして、はじけて飛び出たりもありましたが、ポップコーンの要領で、ふたをして焦げないようにフライパンを時折ふって、香ばしい香りがしてきたら、完成です。
本来は種を洗って、少し干した方がよいようですが、今回はそのまま洗って水気を拭いて炒ったので、少々かたかったですが、ナッツのようで、おいしかったです。
簡単オススメおやつです。