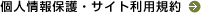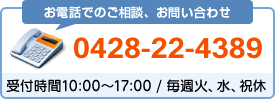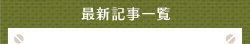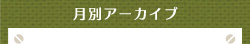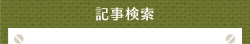2012-05-20
春の味覚

義母の趣味が山菜採りで、毎年この季節になると笹竹の筍を取りに行くのですが、今年も沢山取れたらしく、お裾分けをいただきました。
それに油揚げとしらたき、季節の青物などを入れて、みそ汁風に仕上げれば我が家流の筍汁の出来上がりです^^
笹竹の筍はアク抜きの必要がないので、普通に煮ることが出来る上にサクサクとした歯ごたえが美味しいので我が家の大人気メニューです。
今朝はこの筍汁と納豆と玄米ご飯で朝食をいただきました。
あっさりとしていて、春の香りがして朝から良い気持ちになりました。
春の山菜は苦い物が多いのですが、その苦味が冬の間に身体にたまった毒素を排出してくれるのだと幼い頃に祖母に習ったことがあります。
子ども達には不評な苦味ですが、大人にはあの苦さが逆に美味しかったりするんですよね。
山菜が楽しめる季節はすぐ終わってしまうので、今の内に楽しみたいと思います。
2012-05-19
これ知ってます?
今日は日中に少し空き時間があったので、喫茶店に立ち寄りました。
あまり派手でないこじんまりとした喫茶店だったのですが、そこで懐かしいものを見つけました。
写真を撮ってきたので貼っておきますね。
これです。

私と同世代の方は、「ああ、懐かしい!」と思って下さるはずです。
これは、簡易的な占いの機械のような物なのですが、100円玉を自分の星座のところに入れてレバーを回すと、その日の運勢のようなものが書かれた紙が、小さなカプセルに入れられた状態で出てくるのです。
私は占いを特に信じている訳ではありませんが、昔は喫茶店に行くと必ずと言っていいほどこれがあったので、小銭があまっている時には暇つぶしの遊び感覚で利用したものでした。
今日も懐かしく思い、注文した品が届くまでの間に使ってみようと思ったのですが、財布を開けたら100円玉が無かったので諦めました。
両替してまでもやろうとは思わないんですよね。
そんな主張しすぎない存在感がこの機械の良いところだと思います。
2012-05-18
金環日食

2012年5月21日の金環日食まであと少しですね。
金環日食は、太陽、月、地球が一直線に並んだときに起こる現象で、地球からみると、太陽に月が動いて重なってきます。今回は月が少し小さいので、環のような太陽になるというわけです。
日本では、25年ぶりに見られる現象とのことですが、日本列島(太平洋側)を横断するように、金環食帯に入るのは、約1000年ぶりともいわれています。
2012年の金環日食のあとにみられるのは、2030年の北海道とのこと。
生きているうちにしかも、近くでみられるということは本当に貴重な体験です。
食の始まりは、6時すぎから、金環食の始まりは7時半すぎから約5分間です。
以下におすすめのHPを紹介します。
当日、晴れるといいですね!
金環日食について詳しいページ
http://www.astroarts.co.jp/special/20120521solar_eclipse/
自分の住んでいる場所の金環日食の時間を調べる
http://www.astroarts.co.jp/special/20120521solar_eclipse/itsudoko-j.shtml#nation_title
2012-05-17
春の嵐
この前はもの凄い嵐でしたね!
うちの方は夜通し強い風と雨で物が飛ばされたりして大変でした。
幸い、私の周りでは怪我人は出なかったのですが、今日いつも子供たちと一緒に行っている公園に行って驚きました。
公園に生えていた大きな木が根っこから抜けて倒れており、立ち入り禁止になっていたのです。
大きな木が倒れてしまうなんて、昨晩の風は本当に強かったんだな、と実感しました。
木の根の力はかなり強いと言われているのに、それをこんな簡単に倒してしまうなんて…。
ここで誰も怪我しなくて本当に良かったとしみじみ思いました。
2012-05-10
こいのぼり

こどもの日も終わりましたが、こいのぼりをそこここでみかけました。
日本の古き良き風習はやっぱり、いいものだなあと思います。最近では、たくさんのこいのぼりを川の両岸に渡しているという光景もよく目にしたりしますね。
こいのぼりは、現在では、端午の節句の5月5日まで飾られるもので、鯉が滝をのぼり竜となることができたという故事にちなんで、こどもの成長、立身出世の象徴として始まったそうです。
こいのぼりは夏の季語だそうです。ちょうど二十四節気でいう立夏の頃ですし、青い空に悠々と泳ぐ姿は、光輝くまぶしい夏の到来を感じさせます。
写真は、お気に入りの風景です。大きなこいのぼり。
そして子どもたちが竹馬やこま回しをして遊んでいました。
日本の風習とともに、昔あそびも、子どもたちに受け継いでいってほしいですね。
2012-05-06
金星とすばる
いよいよ、2012年の5月21日には、金環日食がありますね。
金環日食については、また書きたいなと思います。場所や見るための道具なども検討していきたいですね。
夜も寒さを感じなくなってきた4月、ゆったりと星を眺めるのもいいですね。
4月の上旬には、金星とすばる(プレアデス星団)が大接近するのだそうです。
日没後の西の空の高いところに、金星、低いところに木星がみえています。
夜空にひときわ明るい金星を目印に、すぐにすばるをみつけることができそうです。
すばるは、目の良さがわかる星です。
肉眼で6個以上みえれば、視力が良い(1.0以上)といえると思います。
みなさんの視力はいかがでしょうか?
黄金色の金星と、青みのあるすばるの星々。春の星空散歩はいかがでしょうか。
2012-05-03
一緒に料理
私が料理をする度にいつも子ども達が
「一緒に料理したい~!」
と言っていたのですが、まだ幼いこともあり、私が仕事で忙しくゆっくり教える時間が取れないこともあって、ゆで卵の殻むきくらいしかやらせたことがありませんでした。
しかし、今日は私の仕事が休みで、子ども達も大きくなったので一緒に肉じゃがを作ってみました。
流石に包丁で野菜の皮をむくのは難しいので皮をむいたり切ったりするのは私の係で、子ども達には具材を鍋に入れてもらう係と、混ぜる係、それと調味料を入れる係をお願いしました。
混ぜるときに油がはじいて慌てたり、出来てきて味見したときに美味しかった時の子ども達の様子はとても微笑ましいものでした。
出来上がったものを写真に撮ったので載せておきます。
自分達が作った肉じゃがは特別美味しく感じるらしく、大鍋にいっぱい作ったのに一食でなくなってしまいました。
また時間が取れるようだったら色んな料理を子ども達と一緒に作りたいです。

2012-04-30
ダイヤモンドシャープナー
私は美術を専攻して、彫刻刀などを砥ぐために砥石の使い方を習っていたので、今まで自分の家の包丁を砥ぐ時は砥石を使っていました。
荒砥と仕上砥を使って本格的に砥いでいます。
慣れると結構簡単です。
しかし先日、夫が会社のお友達から「ダイヤモンドシャープナー」と言う刃物砥ぎをもらってきました。
どうやらダイヤモンドの粉末を使ったヤスリのようで、2~3回包丁の刃を砥ぐだけで良いのだそうです。
他にも、はさみやキリを砥ぐのに使えるとパッケージ裏に書いてあって、砥石派の私としては
「そんな邪道な」
と思っていたのですが、試しに説明書きの通り刃の両面を軽く2~3回砥いでみると、本当に砥げています!
砥石で砥ぐのはちょっと時間も掛かるし、集中してやらないといけなかったんですが、これなら簡単に砥げますね。
しかし、砥石できちんと砥いだ物に比べると、鋭利さはやや落ちます。
しかし手軽に出来るので、ちょっと切れ味が落ちた時に使うのには良いですね。
良い物を下さった主人のお友達に感謝です^^
2012-04-29
麹を使う

最近、塩麹ブームですよね。お料理に塩を使うかわりに、塩麹を使うと味はまろやかになってとてもおいしくなるそうです。
私は、写真のみやここうじを使って、甘酒や、大根の麹漬け(べったら漬け)、そしてお味噌作りをします。
お味噌は、冬の間に作るのが(寒仕込み)一般的ですが、3〜4月に仕込むこともできます。
(夏の仕込みもあるようです)
暖かくなってくる時期に仕込むと発酵の度合いも違い、仕込む季節によって、味も変わってくるのだそうです。
我が家は、湿気が多いので、カビが入らないように注意が必要なので、かめをみるのにいつもドキドキしてしまいます。
麹が残ったら、塩麹を作ってみようと思います。お湯と塩を入れて待つだけの塩麹。簡単で、体にも良く、美味しい塩麹は、日々の定番になりそうですね。
保存食や、発酵ものに、ますますハマりそうです。
2012-04-27
なつかしい玩具
今日、主人の実家に遊びに行ったら、押入れの中から懐かしい物が発見されました。
これです。

30代とか40代の方は分かるんじゃないでしょうか。
そう、ファミコンカセットです。
もう四半世紀前の玩具です。
懐かしいなぁ…!
当時は放課後に友達の家に集まって、ほんの数個しかないカセットで延々と遊んだものです。
カセットと一緒にファミコン本体もしまってあったので、「まだ使えるかな…?」と思ってドキドキしながらつけたところ、普通に遊べて驚愕しました。
もう20年も使っていなかったのにソフトもハードもどちらも使えるなんて…!
日本の技術力に感嘆の吐息が漏れた瞬間でした。
最近は鍋や家電など外国製の物がとても身近な物になっていますが、それでも世界に誇れる日本の技術力はいつまでも受け継いで行きたいものですよね!