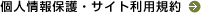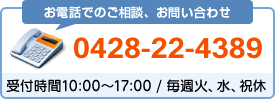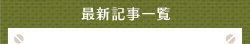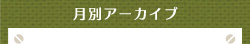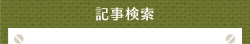2014-07-12
七夕
笹に、折り紙で、ちょうちんや貝細工、星綴りなどの七夕かざりをつけて、短冊を書いて。
今では七夕は、クリスマスのサンタクロースみたいに、神社での神頼みみたいな感じがしますが、
日本で古くからある一年間の重要な節句(五節句)のひとつです。
七月七日は、梅雨の時期で雨が降って織姫と彦星が会えない日が多いですが、
これにも諸説あるようで、旧暦だと七夕は8月半ばにあたり、暑くて雨の降らない真夏に、
雨の水によって穢れが洗われると、雨乞いをしたといういわれもあるようです。
街にもたなばた飾りがあるところもみかけますね。
願い事が現実的だったりすると、これでいいのかと思ったりもしますが(笑)、
子どもたちの書いた短冊をみると、「にじをみたいです」と。かわいいですね。
日本の風習はいいですね。
2014-07-03
紫陽花の花

一年中あるというのに、花が咲くと目が向くのはなんだか気がひけますが、
やっぱり人は変化に富み、美しいものが好きということなのでしょうか。
報告遅れましたが、今年もアジサイの花が咲きました。
毎年家のあじさいは白いのですが、今年は少し青みがかかっている感じがしました。
先月鎌倉へ行ったのですが、梅雨の時期の紫陽花の見事なお寺は大変な混雑でした。
この時期にお寺では、紫陽花をみるために行列ができ、ぞろぞろ歩くといった感じです。
何百株もある紫陽花はそれは見事でしたが、あまりの人の多さにびっくりしました。
ともすれば、雨が続いて億劫な気分にもなるこの時期。
彩りを添えてくれる紫陽花の花に、元気づけられるような気がします。
とは思いつつ、先月は雹が降ってた地域もあっての変な天候でもあり、早く夏がこないかなと待つ気分です。
2014-06-29
クモの子を散らす

閲覧注意、でしょうか。
今の季節、冬を卵で越したクモの卵から、クモの子が孵って固まって過ごしています。
近くに寄ると、振動などで反応し、バッと小さなクモの子がまわりに四方八方に散ります。
その様子から、「蜘蛛の子を散らすように…」とことわざがあるのです。
実際にみると、驚く方もいると思いますが、一匹一匹小さな赤ちゃんクモが健気に生きています。
小さい間は、集団になって、身を守っているのですね。
このあと、脱皮をして、いよいよクモたちは糸を出して風にのって、それぞれ旅に出ます。
ひとつの卵から何百と生まれるクモの子たちも、大きくなるまでに雨風や食べられてしまったりで、生き残れるのは数匹です。
しぜんのきびしさを感じます。
2014-06-25
家のまわりの野草

家のまわりに季節になると生えてくる野草。
そして、それが食べられるとしたら。
種を蒔かなくても、手入れをしなくても生えてくる、そう考えるとありがたいなあと思います。
家のまわりの野草で、代表的な食べられる野草は、フキ。
そしてセリ、ミツバです。
もう少し経つと、ミョウガも出てきます。
八百屋さんにあっても、いいお値段しまうので、買わずにすんで、重宝しています。
今は、大きな葉のミツバがあります。
あと一品ほしいなというときに、おひたしや、吸い物で使ったりしています。
とても便利です。
フキに比べ、セリやミツバは虫食いも少ないです。香りが強い野草だからでしょうか。
ミツバの卵とじはとても美味しいですね。今年もたのしんでいます。
2014-06-20
晴れるか雨か

梅雨どきの今、いろいろなお出かけの予定もお天気が気になるこの頃です。
昔から伝わる、天気のことわざや言い伝えがあります。
家から出て、植物や生きものの様子をみて、晴れかな、雨かなと思ったりする日々です。
なかでも、私が「これだ」と思うのは、夕方(または朝)にクモの巣がかかっていると晴れ、というもの。
クモはエサになる虫を捕まえるために巣を張るのですが、雨降りだと巣が壊れてしまうからつくらないということだと思います。
朝に、巣に水滴がついていても晴れだそうです。
クモの巣のお天気予報、いまのところ、まあまあ当たっている、といったところです。
写真は、あまり関係ないですが、田んぼでみかけたかわいい、くもの案山子です。
2014-06-15
ドクダミの実

ドクダミの花が咲いて、クワの実が地面に落ちる頃になると、もうそろそろホタルが飛び始める頃だなあと思います。
先日、梅雨入りをしましたが、だいたいこの頃に白い花が咲かせます。
白い花といってもこれは、正確にははなびらではなく、がくの部分で、花はまんなかにある黄色い部分、小さな花がたくさん集まって咲いています。
ドクダミは薬効が高く、効能がたくさんあることから「十薬」という別名があります。
薬草として使用するのは、花が咲き始めの頃が良いとされます。草自身のエネルギーが花を咲かせるためにたくさん注がれるからです。
乾燥させた葉をお茶にしたり、そのままを焼酎に漬けて薬にしたり、暮らしのなかでいろいろに使うことができます。
匂いが強く、嫌がられることもあるドクダミですが、実は万能な薬草です。
2014-06-12
天気予報
梅雨入りをして、毎日のお天気が気になるところですが、みなさんはどの天気予報を主にしていますか?
朝のニュース番組でしょうか?
私はネットで調べることが多いのですが、よく使用するのは
「YAHOO天気・災害」です。
このなかの「雨具の動き」というのをよく参考にしています。
近頃の予報はよくできていますね。
降水確率○%という予報をよく目にします。
以前は、降る確率が◯%というふうに思っていたのですが、これは、その地域で雨が降っているのはその地域の◯%という意味なのだそうです。
今年の梅雨はどのくらい続くでしょうか?
雨はありがたくもあるけれど、いろいろと予定がたたなくもなるので、早く上がってほしいなあ。
・YAHOO天気・災害
http://weather.yahoo.co.jp/weather/
2014-06-08
クワの実
クワの実が熟して木にいっぱいなっています。

クワの木は、日本の温暖な気候、関東の里山では先駆的に茂ってくる木のひとつです。
コナラやクヌギの雑木林の足元をみてみると、コナラの幼木に混じって、クワの木の実生(種から芽生えたもの)がそこここにみられます。
なぜかというと、鳥が一役かっていて、クワの実を食べた鳥が、あたりで落とし物(フン)をして、その中の種から芽が出てくるからです。
ですが、その木が大きく成長できるかというとそうではなく、日当りの問題などで淘汰されてゆくわけですが。
成長の早いクワの木はたくましいなと思います。
美味しいクワの実を楽しみに待っているのは、もちろん人だけではないですね。
2014-06-03
新大久保での韓国料理
新大久保近くに用事があったので、寄ってみることにしました。
大勢の韓流ファンの女の子たちで賑わう街になっていて、びっくりしました。
美味しい韓国料理が食べたいと繁華街を歩いていましたが、半ば疲れて、入店。
キムパ(キムパプ)という韓国海苔巻きと、豚バラ肉の甘辛炒めを注文しました。

先付けに、キムチとナムルが出てきました。
辛いものはあまり得意ではないのですが、せっかくなので、辛いものをと注文した炒めものは、あまりの真っ赤な色合いにびっくり。
食べてみると、そんなに辛さを感じませんでしたが、翌日、翌々日は大変でした。。
キムパは、日本の海苔巻きとそっくりでした。調べてみると、キムパは日本の海苔巻きに由来しているそうで、酢飯の変わりに、ごま油を使っているのだそうです。
街も、料理も、本格的な外国料理を食べた実感とその楽しさは更にUP!。
大久保は小旅行気分になれる魅力的な町でした。
2014-05-28
ソラマメとスナップエンドウ

今、畑ではお豆類が元気です。
写真は白い花が咲くスナップエンドウです。
ちなみにソラマメの花は紫色です(品種によります)。
暖かくなって、一斉に花が咲き始めました。
きれいだなあとまじまじと眺めている花です。
はじめて豆類を植えているのですが、スナップエンドウの方が実つきが良いようです。
ソラマメの方は、咲いた花すべてが莢になるわけではないようです。
花が咲き、あっという間に実ったスナップエンドウを先日収穫し、美味しく食べました。
畑で自分で育て、様子をみてきたからというのもあって幸せな気分でした。
ソラマメは花がだいたい終わった頃なので、これからどんな成長をするのかを見てゆくのが楽しみです。