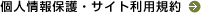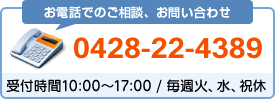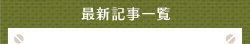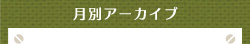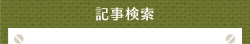2014-03-15
お菓子がいっぱい

先日は我が家の雛人形をご紹介したのですが、今日はひな祭りが近くなると毎年届けられるお菓子の話です。
毎年ひな祭りになると我が家には沢山のお菓子が届けられます。
私の両親や、主人の両親、または義理の兄からなど、いずれも娘へのひな祭りの贈り物なのですが、沢山いただくのでこの時期は
「お菓子を入れている棚が閉まらない!」なんて事態になったりします。
今年も沢山の和菓子を頂きました。
私は和菓子が大好きなのでとっても嬉しい!のですが、流石に食べ切れず、ひな祭りが終わってお雛様を押入れにしまった今でも沢山残っております。
その内の一部を写真に撮ったので載せておきますね。
お饅頭やキンツバ、昔懐かしいきな粉棒などなど…。
毎日食べていたのですがなかなか無くなりません。
まだこの他にも雛あられや桃のお菓子などが沢山あるんです。
お菓子を毎日食べられるのは嬉しいけれど、た、体重が…。
2014-03-12
春の足おと

近くの田んぼに今年も、ヤマアカガエルが卵を産みにやって来ました。
このカエルは、まだ春といえど寒い時期にやってきて卵を産みます。
まだ寒い時期に産むのは、ヘビなどの天敵が少ないからともいわれています。
産んだあとの母さんガエルは、再びもう一眠り(冬眠)するのだそうです。
寒かったり暖かかったりと、三寒四温の今ですが、ふきのとうが咲き、ウグイスが初鳴きが聴こえ、春のあしおとを感じます。
モクレンのふわふわの冬芽が膨らんで、ミズキの冬芽が真っ赤に色づいて、木々の命の息吹にも、寒さで縮こまっている身体を、なんだか背中を押されるような気分です。
去年、はじめて自宅の小さな池に、ヒキガエルが卵を産みにきたのも、もうすぐの時期です。
今年もやってきてくれるかな。
だいぶ楽しみです。
2014-03-10
もずのはやにえ

はじめて見る方は、これはなんだとびっくりするでしょうね。
今年初めてのモズの早贄(はやにえ)を先日みつけました。
モズは小さな狩人ともよばれています。
スズメより少し大きいくらいの大きさで、口ばしが鋭く獲物を捕まえるのに適しています。
「ケケケケッ」という高鳴きをするので、いるな、とわかります。
大雪のあとにみられたので、雪の下にいろいろが埋もれていて、モズも餌に困っていたろうと思います。
雪解けすぐに、さっそく活動を開始したところといったところでしょうか。
今回みつけたのは、カラタチのとげに刺したカナヘビ。
モズは餌となるバッタやカマキリ、トカゲなどを、枝に刺してとっておくという習性があります。
今年はなかなか見つけることができなかったので、モズが元気な様子を感じて安心しました。
2014-03-08
2月の大雪は大変でしたね

2月の2週に渡る大雪は、とっても驚きました。。
やっと街の残雪もほぼ無くなり、やっと落ち着いたという感じですね。
大雪の際には、
16年、20年、35年、45年、100年ぶりと…どんどんニュース告知の年数が増えてゆき、異常気象ともいわれました。
この青梅市や奥多摩町、近県では山梨県などでも多くの被害が発生しました。
一度目の雪はさらさらした雪。
2度目の雪は重たい雪で、その翌日の小雨・・・・
木々が倒れたり、カーポートや落雪の被害がでました。
東京都の最深積雪量としての記録は、1890年代の46㎝なのだそうですが、
なぜこんなに雪が降ったのかは、地球温暖化や、黒潮の蛇行ともいわれていましたが、今の段階で要因が決められてはいないようです。
100年単位、もっと長い時間単位の気象の変化の流れの一端(地球寒冷化)、ともいわれているそうで。
近く地球は小氷河期入りするという見方もあるようで、今後とも様子をみていかなければいけないかもしれません。
いつでも心積もりと、災害に備えた自己管理の徹底が必要と心から思いました。
2014-03-05
プロの技

2014-03-04
梅の開花

今日は、あったかいな。もう冬はおわってしまったみたい、という日でした。
もう梅の花が咲いているのに気がつきました。
今年は、寒いといわれていたけど、今のところ積もるほどの雪は降っていないし、去年よりもあたたかいように思います。
梅の花をみると、さっそくハチやチョウが蜜を吸いにたくさん集まっていました。
冬は、あまりみられなくなる虫たち。
ちゃんと花が咲いたことがわかっているのだなあと思うとすごいなあという思いとともに、どうしてわかるんだろう(花の匂い等とは思いますが)、その小さな生きものたちのいのちに感動します。
もうすぐ、フキノトウも顔を出すでしょう。
春のはじまりは、その小さなたくさんの変化に感動します。
2014-03-03
ひなまつり

今日はひな祭りですね。
この季節になると毎年スーパーやデパートには桃色の可愛らしいお菓子が並び、買い物に行くたびに微笑ましい気持ちになります。
色とりどりの雛あられや三色の菱餅などは、いかにも女の子が好きそうなカラーリングですよね。
小さな金平糖や可愛らしい飴なども見かけますが、食べるのがちょっと勿体無いような可愛らしさです。
我が家には今年小学校に上がる娘が一人いるので、毎年節分が終わると居間に雛人形が飾られます。
この雛人形は娘の初めてのひな祭りに私の父が買ってくれた物で、可愛らしい顔をしているので、私も娘もお気に入りの人形です。
今日はちょっと仕事が忙しくてひな祭りのパーティーは出来なかったのですが、帰ってから娘と一緒にお雛様の前で生菓子を食べました。
ひな祭りの由来には諸説あるようですが、自分の子どもが元気に育って欲しいという親の気持ちは今も昔も変わりませんね。
2014-02-28
2月も終わり
今日で2月もお終いですね。
2月は他の月に比べて早く終わってしまうので、毎年2月の末日になるとなんだか得したような損したような不思議な気分になります。
長かった冬ももうお終いですね。
3月なれば本格的に春が到来します。
春になったらお花見が出来ますね。
山菜も出回るので美味しい天ぷらやお浸しも楽しむことが出来ます。
それに春の陽気というのは何とも気持ちが良いものですよね。
日向ぼっこをしながらお昼寝するにも春は最高です。
昔から「春眠暁を覚えず」と言いますが、暑すぎず寒すぎずのんびりするのに最適な春は、今の人も昔の人もちょっぴりダラダラしたくなってしまうものなのかも知れません。
でも、3月は年度末でもあり節目の月ですから、経理の人や決算書を書いたりする必要のある人は大変な月でもあります。
また、4月から新生活が始まる新入生や新入社員の方は新しい生活の準備をしなければなりませんね。
いずれにしても人間は体が資本です。
素敵な春を過ごせるよう、体調管理をしっかりとして最後の寒さを乗り切りましょう!
2014-02-21
糸つむぎ

去年、和棉の種を蒔いて育てました。
花が咲いて実がなり、はじけて綿がでてきた様子はとても綺麗でした。
ふわふわの綿を収穫して、中の種をとりました。綿繰り機を使うと、とても作業が早いです。
そのあと、空気をいれるように繊維をほぐし(綿打ち/これがなかなか大変な作業です)、いよいよ糸紡ぎになります。
スピンドルという糸紡ぎのコマを使って、手紡ぎ。
はじめはなかなか上手くいかずに糸が切れてしまったりもしますが、コツをつかんで慣れてくると、その手紡ぎの意味に思いふけります。
ガンジーは糸を紡ぐことを非暴力の象徴として続けました。
「衣食住」の「衣」がいちばん前に来る意味を考えてみたいと思います。
2014-02-18
ハイボール

以前、テレビでハイボールの特集を見ました。
ハイボールは、日本ではウイスキーをソーダ水で割ったもの。
最近、若い人にも人気ですよね。
東京の下町の居酒屋で親しまれているという、希釈する謎の液体。
その味の正体を、どのお店でも教えてくれないのだそうです。
下町のある場所で、流通のすくないその液体。
とても気になったので、ネットで探して注文してお取り寄せ。
飲んでみました。
その液体自体で飲むと、不思議な味がしますが、ウイスキーや、焼酎で割るとおいしい!
お酒と炭酸を割ったものよりも、飲みやすくなったように感じました。
割り液なので、お酒のかさ増しにもなったりして、お得かもしれません。
まわりの人にも、好評でした。