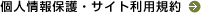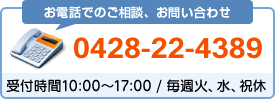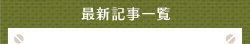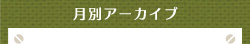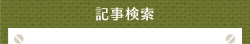2012-12-20
ネックウォーマ
娘が毎日寒い寒いと言うので、こんなものを買ってみました。

ネックウォーマーです。
すぽっと頭から被るものなのですが、用途はマフラーと一緒です。
首部分を温めることが出来るので、襟ぐりが大きく開くような服を着る方にはおすすめの防寒アイテムです。
もこもことしてて、見た目も可愛いです。
冷えは下半身や首元から来るってよく言いますよね。
だから、ネックウォーマーやレッグウォーマーは結構効果的らしいです。
娘も気に入ったようで、「あったかいし、ふわふわして気持ち良い」と、好んで着けています。
買ってよかった。
そろそろセンター試験ですが、受験生の方も、夜勉強する時などにつけると良いかもしれませんね。
本番前に風邪ひいていられませんからね。
受験生の皆さん、暖かくして、ラストスパート頑張って下さい!
2012-12-18
ゆず茶
ゆずは、ビタミンCがたっぷり含まれていて、風邪の予防にもぴったりです。

特に果皮にビタミンCが豊富に含まれているそうです。
コラーゲンも含まれていて、美肌効果もあり女性にはうれしい果実です。
ゆず茶の作り方はいろいろあります。煮ても良いのですが、漬け込むのがかんたんです。
ゆず茶は、種を除いて果皮と果肉を細かく刻んで、はちみつや氷砂糖で漬け込むだけでかんたんにできます。
2週間ほど置くと、食べ頃になります。保存は常温でも可能ですが、冷蔵すると安心です。
種は、化粧水にも使えるし(先述)、ゆずは捨てるところなくたのしむことができます。
寒い冬に、お湯を注いで作るゆず茶は、体の芯までぽかぽか温まります。
おやすみ前にあったかいゆず茶を飲むのがおすすめです。
もう少し先の話ですが、他に花粉症にも良いとされる栄養素も含まれています。
初冬から春を迎えるまで、ゆずにはとてもお世話になりそうです。
2012-12-15
大根

寒い冬。
畑でも野菜の収穫が少なくなる季節。昔の人は、保存食を作り、冬のこの時期に備えたものです。
今でも保存食として馴染みの深いのが、お漬けもの。
なかでも、大根を使った、たくわんや、はりはり漬けなどは、簡単に作ることができます。
私は、12月に漬け込んで、新年から食べるのが毎年の習慣です。
たくわんなら、一週間ほど干して、くの字に曲がるくらいになったら、漬けどき。
はりはり漬けなら、四つ割りにして、二週間ほどからからに干します。
はりはり漬けは、乾いた大根をお湯でもどして、醤油、酢、砂糖、昆布で作った漬け汁に漬け込むだけなので、とても簡単でおすすめです。
一緒に漬けた昆布も味がしみておいしくなります。ご飯のお供に最適です。
保存食の便利なところは、常温保存できること。
私は、たくさん仕込んで、一年近くかけて食べています。
お弁当にちょっといれたりと、なかなか重宝します。
他にも、切り干し大根にしたりと、冬の時期、大根は大活躍のお野菜です。
2012-12-12
主人のセーター

先日、冬服を整理していたら懐かしいものを見つけました。
赤ちゃん用のセーターなのですが、数年前に主人の母から頂いたもので、主人が赤ちゃんの時に着ていたものだそうです。
だとすると、もう30年以上も前のセーターなのですが、ところどころ毛玉は付いているものの、まだ充分着ることが出来ます。
肘の部分に継ぎ接ぎがあって、それがまた時代を感じさせます。レトロっぽくて可愛いです。
首のタグには『1~2才用』と書いてあります。
カラーやデザインが可愛いので、女の子でも着ることが出来そうですよね。
我が家の子ども達は、残念ながらこれを着ることが出来る年齢は卒業してしまったのですが、来年妹に子どもが生まれる予定なので古着でも良かったらあげようかな。
2012-12-10
星の王子様(映画)

毎年の年末年始に、ゆっくりと見たいなと思う映画が、「星の王子さま」です。
「星の王子さま」は、サン・テグジュペリの書いた、名作童話です。
世界に数ある本のなかで、聖書の次に多くの人に読まれている本が、「星の王子さま」なのだそうです。
読む度に、感動する場所がちがうような、童話といえど奥深い本です。
この映画は、この童話の実写版なのですが、本の世界観をそのままに表現された、ミュージカル映画です。
主役の王子さまの子どもがとてもかわいいです。
他にも、ヘビ役のボブ・フォッシーなど名優が出ていることで、見事な世界観を引き出しています。
年の終わり、年の初めに、優しい気持ちになれる映画です。
お子さんと一緒にみると、素敵な思いを共有できそうです。
2012-12-07
クリスマスツリー
今年ももう12月ですね。
この子が活躍するシーズンです。

クリスマスツリーです。
我が家のクリスマスツリーは、長女が生まれた年に義父から頂いたもので、小型なのですが白い本体が電源を入れると色々な色に変わるので、皆でとても気に入ってます。
綺麗です^^
今年は早めに押入れの奥から出してあげました。
この子の出番になると、いよいよ「冬だなぁ~!」って感じがします。
冬は寒くて嫌ですが、だからこそ「暖かい」ということが嬉しく感じますよね。
ストーブの前で本を読んだり、こたつに入りながらテレビを見たりすることに幸せを感じるのは、冬が寒いからこそです。
私は、実は結構この幸せって好きなんです。
夕食が終わって、寝るまでの間にこたつでのんびりする時とか、家事が一段落した午後に夕食のメニューを考えながら
ストーブの前で料理の本を捲る瞬間は格別です。
日本にいると、四季折々の楽しみ方が出来て豊かですね。
2012-12-03
博物館
子ども達が冬休みに入ったので、先日一緒に博物館に行ってきました。
博物館なんて何十年ぶりでした。
昔は博物館というと、薄暗くてどこかちょっと怖いような空気を感じたものですが、今の博物館はとてもお洒落で綺麗で驚きました。
内装だけでなく、展示品の展示方法も実に良く考えられていて、大人でも楽しめる空間になっていました。
昔は博物館にある展示品には触ったりすればとても怒られたものですが、今の博物館は実際に触ったり動かしたりしても良いものもあるんですね。
内容も充実しており、2時間程いましたが飽きなかったです。

写真は展示してあった人力車です。
乗ることは出来ないのですが、触ることは出来ました。
この他にも昔の商家が博物館内に建てられていたりして、中に入ったり出来ました。
子ども達と一緒にまた行きたいです。
2012-12-01
オナモミ

春夏に花が咲き、秋に実が成り、種を結ぶ。
多くの植物が、このようなサイクルで四季を過ごし、寒い冬は種で土の中で過ごし、暖かくなる春を待っています。
秋、原っぱを歩くと、足元にいっぱいの種がくっついたという経験はありませんか?
たぶん、多くの人が子どもの頃、服にいっぱい種をつけて帰った、ということがあることと思います。
今の季節、道ばたの野の草をよくみると、まだ種がかろうじて残っているものがあります。
「くっつき虫」とよばれるそれらは、その名のごとく、動物や、人にくっついて、距離を伸ばし、また新しい地で、芽を出すのが目的です。
くっついた種をよくみてみると、先端が曲がっていて、くっつきやすい形になっています。
写真はオナモミの実ですが、この鉤針のような形は、私たちの日常の暮らしの上で使っているもののヒントになっています。
マジックテープがそれです。
他のくっつき虫たちも、いろんな形をしています。じっくりみると不思議がわかって楽しいですね。
2012-11-28
秋のサラダ
今日、スーパーに行ったら、店員さんがお肉売り場の試食コーナーでちょっと珍しいメニューを出していました。
2種類のさつま芋と揚げウインナーを使ったサラダです。
レタスの上に、一口大に切って蒸し焼きにしたさつま芋と紫芋が乗っており、その上に油で揚げたウインナーと紫玉葱が乗せられていました。
さつま芋の黄色と紫芋の紫が何とも秋らしくて綺麗だったので味見させてもらったのですが、ほっこりと甘いお芋の味と、紫玉葱の香り、そして揚げウインナーのコクが見事にマッチしていてとても美味しかったです。
作り方を聞いて、早速家で作ったのですが、家族にも好評で良かったです。
秋といえばさつま芋ですが、さつま芋の料理って蒸かすか大学芋にするくらいしか思いつかないので、今日は新しいレシピを得ることが出来て嬉しかったです。
今日のレシピはこの秋に何度が我が家の食卓に登場しそうです^^
2012-11-22
紅葉

街路樹が更に色づいてきましたね。
道を通るたびに黄色やオレンジ、赤に染まった樹の葉が目を楽しませてくれます。
そんな街路樹を眺めるのも楽しいのですが、まとまった紅葉が見たくなって、今日は紅葉が綺麗だと評判の公園へ行ってきました。
天気の良い日にはお弁当を持って紅葉の下で食べるのも楽しそうですね。
紅葉の時期は桜の時期と同様とても短いので、見逃すと来年まで見ることが出来ません。
更に、本格的な寒さがやってくる頃になれば、屋外でのんびりするなんて出来なくなりますから、今の時期に楽しんでおきたいですね。
私の母は東北出身なのですが、この季節になると東北地方では屋外で鍋料理を作って皆で楽しむ行事があります。
その県により呼び名が違い、福島では「芋煮会(いもにかい)」、秋田では「鍋っこ(なべっこ)」などと言うそうなのですが、少し肌寒い秋の時期に暑い鍋物を友達と一緒に囲むのはとても楽しいでしょうね。
今度友達と一緒にやってみたいと思います。